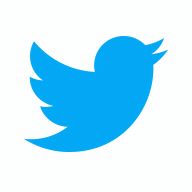旧正月・春節・立春の意味と違いについて
「旧正月」とは旧暦(太陰太陽暦)のお正月(1月1日)のことです。
日本では現在、新暦(グレゴリオ暦)が採用されていますが、明治の改暦までは旧暦が用いられていました。
太陰太陽暦とは、月の満ち欠けと太陽の動きを入れた暦です。
「春節(しゅんせつ)」とは、中国での旧正月のことで、
旧暦1月1日に始まり15日間続く祭りのこと。
ちなみに2020年は1月25日が一日目となります。
月の満ち欠けにより変わるため、毎年同じ日付ではありません。その年のカレンダーで確認しましょう。
では「立春」は?
「立春(りっしゅん)」とは
二十四節気の一つであり、旧暦ではこの日が1一年の始まりとされ、暦のうえでは春になります。
二十四節気は、太陽の動きをもとに24等分したもので、古代中国で考案されました。2020年は2月4日が立春です。
つまり月の動きを基準にした「旧正月」と「春節」は同じ意味ですが、太陽の動きをもとにした二十四節気の「立春」は別物ということです。
では「立春」以外の二十四節気の意味と由来は?