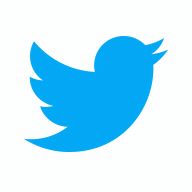「愛嬌」とは
読み方:あいきょう
意味:にこやか、かわいらしいこと、憎めない表情しぐさ
由来:仏や菩薩の優しく温和な慈愛に満ちた様子を指す
「愛敬相(あいぎょうそう)」という仏教用語転じ、室町時代には「あいきょう」といい、「敬」を「嬌」と当てるようになりました。
「愛想」とは
読み方:あいそう、あいそ
意味:人当たりのいい態度、人に対する好意や、勘定を指します
「愛嬌」と「愛想」の違いは?
愛嬌はその人がもつ内面の性質について使い、
愛想はその人の仕草や表情、表面的な動作に使います。
では、振りまくのは?
答え:愛嬌を振りまく
意味:だれにでも愛想よくすること
「愛嬌」が「愛想」と同義とされ「愛想を振りまく」という使い方も多くみられますが、本来は「愛嬌をふりまく」です。