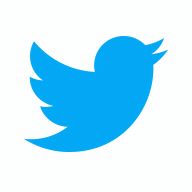「二十歳」と「弱冠」は全く同じ意味ではありませんが、とても似ている表現です。
「弱冠」の由来:
古代中国で男子20歳を「弱」といい、元服して冠をかぶる元服式を行ったことに由来。(他にも辻髪・志学・弱冠・而立・不惑・知命・耳順・従心など年齢に由来する表現があります。「不惑」については→こちら)
本来の意味:
男子20歳の異称。(女性に使うのは適切ではありません。)
また、成年に達することです。
現在では「20歳前後の若い人を指す」言葉として使われることが多くなっています。
ちなみに、「二十歳」は「はたち、にじゅっさい、にじっさい」と読みますが、「20歳」と表記した場合は「はたち」とは読みません。