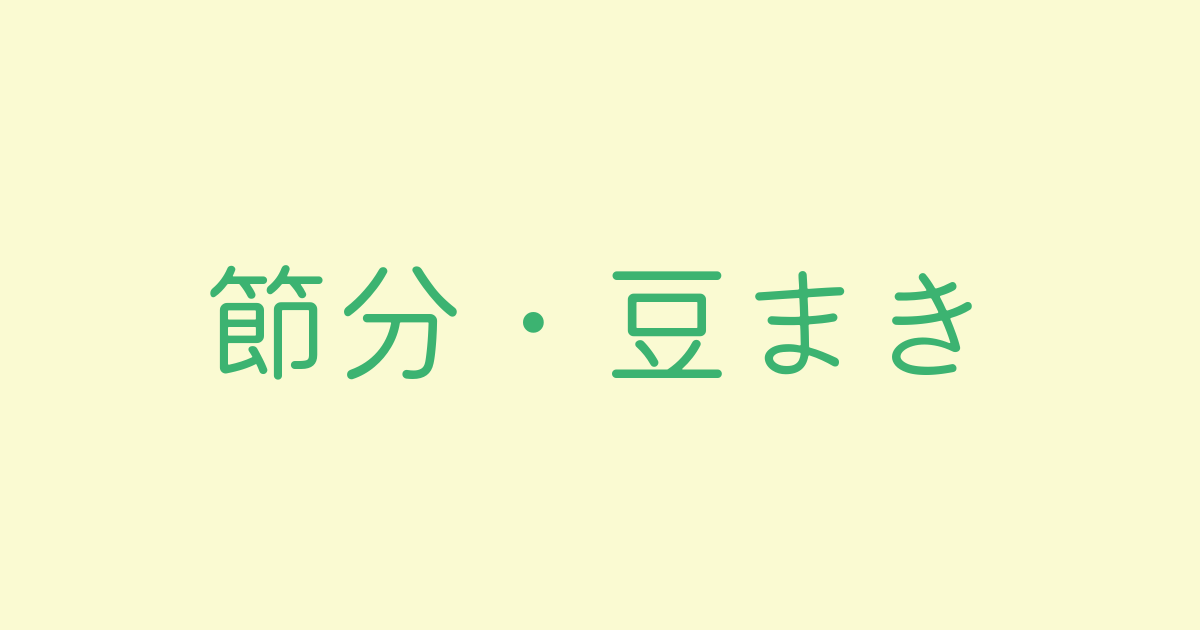「立春大吉日 喼急如律令」とは
読み方:りっしゅんだいきちじつ きゅうきゅうにょりつりょう
「立春大吉」とは、
季節の変わり目に邪気を追い払い無病息災の意味で使われます。
「立春大吉」が左右対称の文字なので、裏から見ても同じに見えます。
そのため、節分では玄関にこれを書いたお札が貼ってあると、鬼が家に入っても、振り返った時また「立春大吉」というお札を目にし「この家にはまだ入っていない」と勘違いをして逆に出ていく。
つまり鬼が入ってこないということから、厄除けの意味として使われているのです。
「喼急如律令」とは
中国の漢時代に公文書の末尾に記される言葉で、
意味は「急いで律令のごとく行え」です。
陰陽師や祈祷師が、悪霊退散などの呪文の最後に用いました。
つまり「立春大吉日 喼急如律令」とは
「季節の変わり目、一年の始まりのめでたい日の立春、厄災は立ち去り、願いが早急にかないますように」という意味なのです。
「立春大吉」のお札は神社でいただいたり、自分で書いて貼るのも良いそうですので、是非取り入れてみるのもいいですね。では、2020年の立春はいつ?