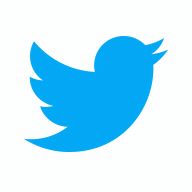身近な野菜とまと、ひらがな、カタカナで表記されてますが、漢字では何と書くのでしょうか?
調べてみると、トマトを表す漢字は5つもありました。
唐柿(からがき、とうし)
蕃茄(ばんか)
小金瓜(こがねうり)
赤茄子(あかなす)
珊瑚樹茄子(さんごじゅなす)
それぞれの由来をご紹介いたします。
「唐柿」
海外の意味の「唐」と、見た目が「柿」に似ていることから。
とまとは中国経由で日本に入ってきたのですが、当時は「唐柿」と言っていたようです。
「蕃茄」
中国語で、とまとのことを「蕃茄」と表し、中国から入ってきた漢字のようですが、「蕃」は外国という意味、「茄」はナス(とまとはナス科)で外国(西洋)からきたナスっということでしょうか。
「小金瓜」
小金色の瓜という見た目から。
「赤茄子」
見た目の色と形から。
「珊瑚樹茄子」
実がなる様子を言い当てた漢字から。
海外から入ってきたトマトですが、色、形と表す漢字が面白いですね。
ちなみに生産量日本一は熊本県、二位は北海道、三位は茨木県(2017年)です。