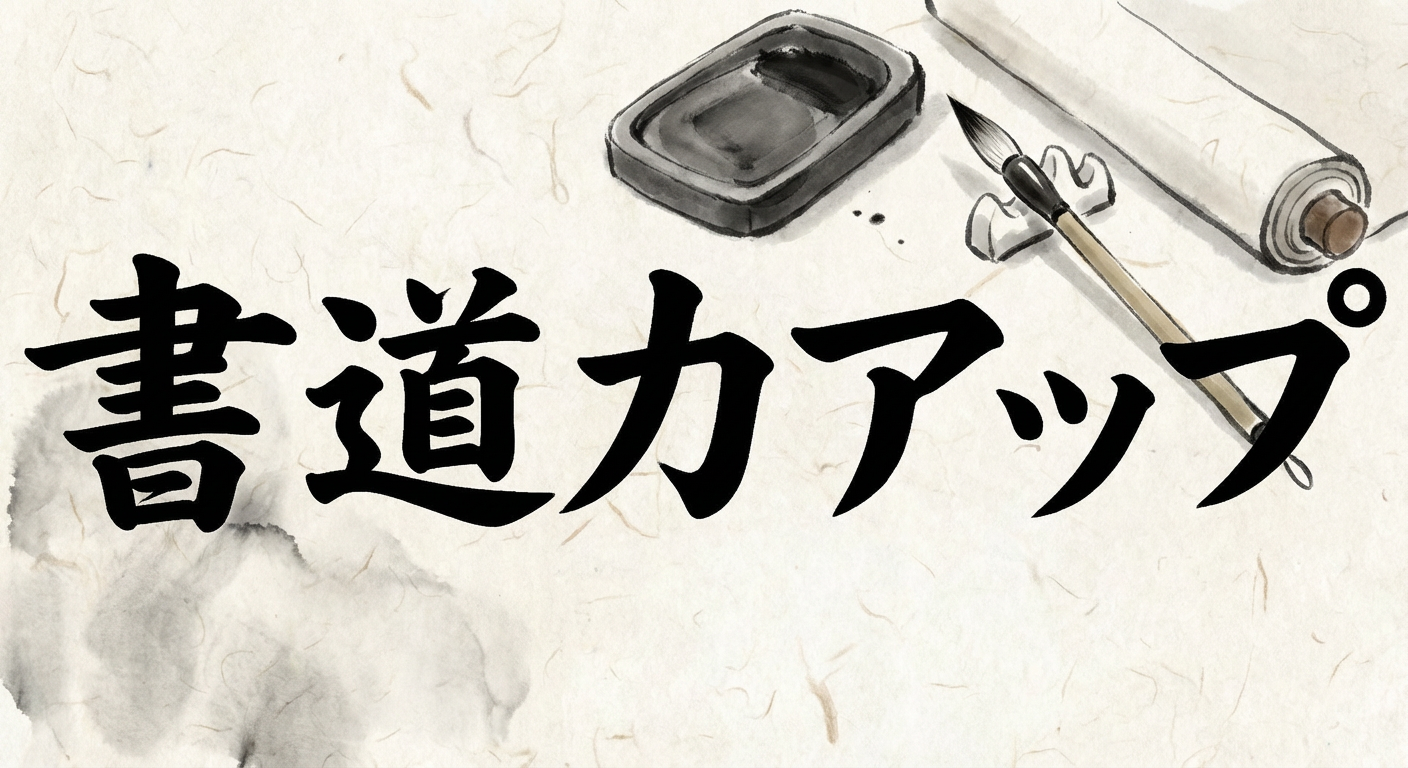例文・使い方一覧でみる「芭」の意味
スポンサーリンク...芭蕉の俳諧を愛する人の耳の穴をあけねばならぬ所以(ゆゑん)である...
芥川龍之介 「芭蕉雑記」
...この芭蕉の三様の画趣はいづれも気品の低いものではない...
芥川龍之介 「芭蕉雑記」
...芭蕉は「虚栗(みなしぐり)」(天和三年上梓)の跋(ばつ)の後に「芭蕉洞桃青」と署名してゐる...
芥川龍之介 「芭蕉雑記」
...芭蕉(ばしょう)...
梅崎春生 「幻化」
...そういう見地からいうと芭蕉は時代の寵児(ちょうじ)だともいえます...
高浜虚子 「俳句とはどんなものか」
...昔芭蕉の弟子に許六(きょりく)という人がありました...
高浜虚子 「俳句の作りよう」
...水芭蕉は馬も食わないと言ってたが...
高見順 「いやな感じ」
...それぞれ芭蕉の葉であった...
蒲松齢 田中貢太郎訳 「翩翩」
...……芭蕉の言葉に...
種田山頭火 「行乞記」
...あそこの温泉の位置は芭蕉(ばせう)の行つた時とは丸で違つてゐて...
田山録弥 「行つて見たいところ」
...かなり数奇(すうき)の生涯を体験した政客であり同時に南画家であり漢詩人であった義兄春田居士がこの芭蕉の句を酔いに乗じて詠嘆していたのはあながちに子供らを笑わせるだけの目的ではなかったであろうという気もするのである...
寺田寅彦 「思い出草」
...その修善寺(しゅぜんじ)における数吟のごときは芭蕉の不易の精神に現代の流行の姿を盛ったものと思われる...
寺田寅彦 「俳諧の本質的概論」
...それは芭蕉(ばしょう)とその門下の共同制作になる連句である...
寺田寅彦 「ラジオ・モンタージュ」
...芭蕉のイデアした哲学は...
萩原朔太郎 「郷愁の詩人 与謝蕪村」
...昼は芭蕉扇を腹の上にのっけて夕方まで眠りつづけ...
久生十蘭 「平賀源内捕物帳」
...源順(みなもとのしたごう)の『倭名類聚鈔(わみょうるいじゅしょう)』にも芭蕉を和名発勢乎波(バセヲバ)と書いてあるところをみると...
牧野富太郎 「植物一日一題」
...「清音閣主混外上人見贈芭蕉数根...
森鴎外 「伊沢蘭軒」
...芭蕉は義仲をどう見たか晩年の巴が...
吉川英治 「随筆 新平家」
便利!手書き漢字入力検索
- 野球選手の桑田真澄さん: 巨人一筋のレジェンドが独立リーグ球団のCBOに就任 ⚾
- お笑い芸人の藤森慎吾さん: 家族ができて公園の偉大さに気づいたチャラ男 😊
- 声優の石原良さん: 声優・ナレーターで青二プロダクション創立メンバー死去94歳😔