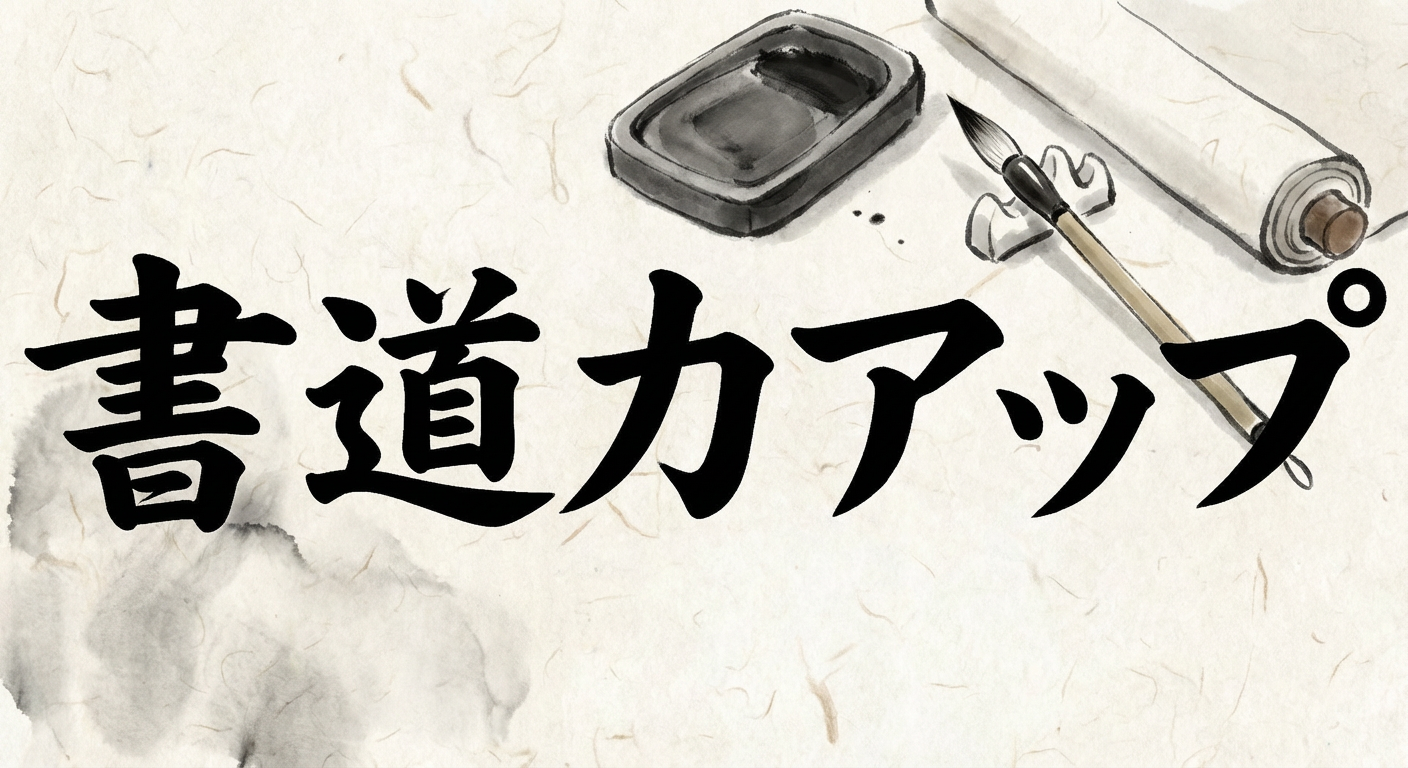例文・使い方一覧でみる「明応」の意味
スポンサーリンク...明応年中、近衛尚通の子政信、家を継ぐ...
太宰治 「津軽」
...明応七年に三十四歳で帰朝して...
中里介山 「大菩薩峠」
...明応七年に地借りをして...
原勝郎 「東山時代における一縉紳の生活」
...実隆の家は明応九年六月下旬の火災に類焼したのであるから...
原勝郎 「東山時代における一縉紳の生活」
...明応五年には実隆も堪忍しかねたらしく...
原勝郎 「東山時代における一縉紳の生活」
...けれどもそれまでの好みを考えると、そうもできなかったらしく、明応八年四月、元盛の十三回忌に、盛豊が形のごとく僧斎を儲けた時に、実隆は家計不如意のため、志があっても力が及ばぬ、十分な補助ができぬのは遺憾だと歎いている...
原勝郎 「東山時代における一縉紳の生活」
...明応四年ごろ玉泉という者をもってこれに任じたことがあり...
原勝郎 「東山時代における一縉紳の生活」
...しかるに明応五年美濃の喜田城陥落し...
原勝郎 「東山時代における一縉紳の生活」
...土岐の明応五年の没落を報じて来たのもまたこの男である...
原勝郎 「東山時代における一縉紳の生活」
...明応五年正月からして阪本に苧課役を月俸にして沙汰をすることにしたと日記に見えているが...
原勝郎 「東山時代における一縉紳の生活」
...翌々明応七年十五歳の時である...
原勝郎 「東山時代における一縉紳の生活」
...明応六年といえば彼の遯世(とんせい)に先だつこと二十年である...
原勝郎 「東山時代における一縉紳の生活」
...また明応四年八月の「大内家壁書」の中に用いられているものであるが...
穂積陳重 「法窓夜話」
...(中略)明応四年乙卯(いつぼう)八月 日沙弥 奉正任左衛門尉 同武明五六 経済学経済学は...
穂積陳重 「法窓夜話」
...明応七年兵燹(へいせん)にかかりて枯しを社僧祠官等歌よみて奉りたれば再び栄生せりといへり...
森鴎外 「伊沢蘭軒」
...あの明応の動乱が平定して後に...
柳田国男 「海上の道」
...明応文亀年間、平田将監という者があって、剣及び十手術に長じ、美作吉野郡の竹山城城主新免氏に仕えたのが中興の人となっている...
吉川英治 「随筆 宮本武蔵」
...やがて明応四年(一四九五)には小田原城を...
和辻哲郎 「埋もれた日本」
便利!手書き漢字入力検索
- 野球選手の桑田真澄さん: 巨人一筋のレジェンドが独立リーグ球団のCBOに就任 ⚾
- お笑い芸人の藤森慎吾さん: 家族ができて公園の偉大さに気づいたチャラ男 😊
- 声優の石原良さん: 声優・ナレーターで青二プロダクション創立メンバー死去94歳😔