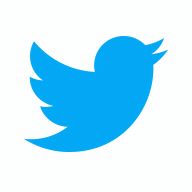「コロナ禍」の「禍」とは?
「禍」について
読み方:か、わざわい、まが
意味:災いや、不幸のこと
使い方:「水禍」「惨禍」
「禍(わざわい)を転じて福と為す」
「禍々(まがまが)しい」
「コロナ禍」の読み方は、「コロナか」です。
ちなみにコロナ禍の「禍」は、過去にも「コレラ禍」「ペスト禍」など伝染病が流行った時代にも使われています。
また「禍」とよく似た漢字が「鍋」「渦」「過」などありますが、「コロナ『禍』」ですので間違えの無いようにしたいですね。
新型コロナウイルスが一日も早く「しゅうそく」しますように。この場合「しゅうそく」は、「収束」「終息」「集束」?