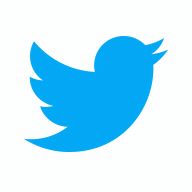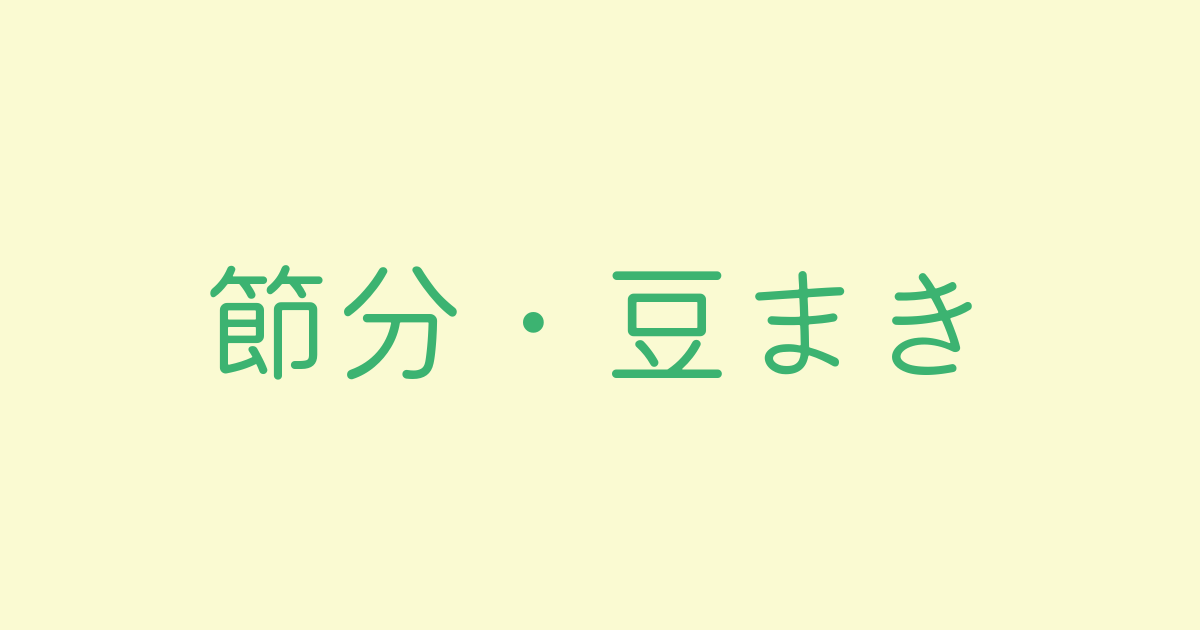海や魚のつく名前はたくさんありますが、
「翻車魚・浮木・曼波魚」から何を想像しますか?
今回はこの二つについてご紹介します。
「翻車魚」
読み方:マンボウ
別名:「浮木(うきぎ)」
ちなみに漢字文化圏では「曼波魚」とも表記されます。
由来:諸説ありますが、体が丸いため「円坊鮫(まんばうざめ)」からきているという説。方形(四角形)という意味の「満方」かからきているという説など。
「浮木(うきぎ)」の由来:水面に体を横にして浮かぶ様子(体についた寄生虫を太陽にあてて滅菌するためともいわれる行動)から。
マンボウは泳ぎはあまり上手ではなく、皮膚が弱いデリケートなお魚で飼育も大変だとか。そのため角をなくすなど工夫されたマンボウ専用の水槽で飼育されています。
水族館でマンボウを見る機会があったら、漢字も思い出してみるとまた違う姿に見えるかもしれませんね。
ちなみにマンボウは食用としても美味らしいですが、鮮度がすぐ落ちるためなかなか流通しないお魚だそうです。