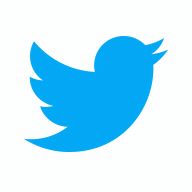「螻蛄になる」は何と読むでしょうか?
答え・・・
読み方:「おけらになる」
意味:お金がなくなる。無一文になる。
使い方・例文:「賭け事で負けて螻蛄になった」
「今月は出費が多くて螻蛄だ」
「螻蛄」の語源・由来:オケラとは昆虫の「ケラ(飛蝗の仲間)」のこと。
ケラは前から見ると万歳をしているように見えます。
その姿が、無一文になってお手上げという風に見立てたことが由来という説。
またもう一つには、オケラという薬草があります。根の皮を剥ぎ使うのですが、その皮を剥ぐが、ばくちに負けて無一文、丸裸にされる者を連想されることから「オケラ」という説もあります。
では、ケラは飛蝗の仲間なのですが、飛蝗とは何でしょう?