マスカットは、「陸の真珠」「葡萄の女王」とも呼ばれるブドウですが、漢字で表すと?
マスカット(英語:Muscat)は麝香(マスク、ムスク)のような強い香りが特徴で、ラテン語のmuscus(麝香)が語源。この香り高いぶどうを漢字にすると?
麝香葡萄 です。
では、キウイを漢字にすると?
マスカットは、「陸の真珠」「葡萄の女王」とも呼ばれるブドウですが、漢字で表すと?
マスカット(英語:Muscat)は麝香(マスク、ムスク)のような強い香りが特徴で、ラテン語のmuscus(麝香)が語源。この香り高いぶどうを漢字にすると?
麝香葡萄 です。
では、キウイを漢字にすると?
梅雨が明けて、うだるような暑さが続いております。
この「うだる」とは何でしょう?
「うだる」とは?
漢字:茹だる
意味:湯で十分に熱せられる、煮ること。
暑さで体がぐったりすること。
「茹だる」は「ゆだる」とも読めます。
「卵が茹だる(ゆだる)」「銭湯で茹だる(ゆだる)」など。
では「うだるような暑さ」の「うだる」は?
「ゆだる」が転じたものです。あまりの暑さで頭が茹で上がってしまうような様。
ぐったりするほど不快な暑さを言っているのですね。
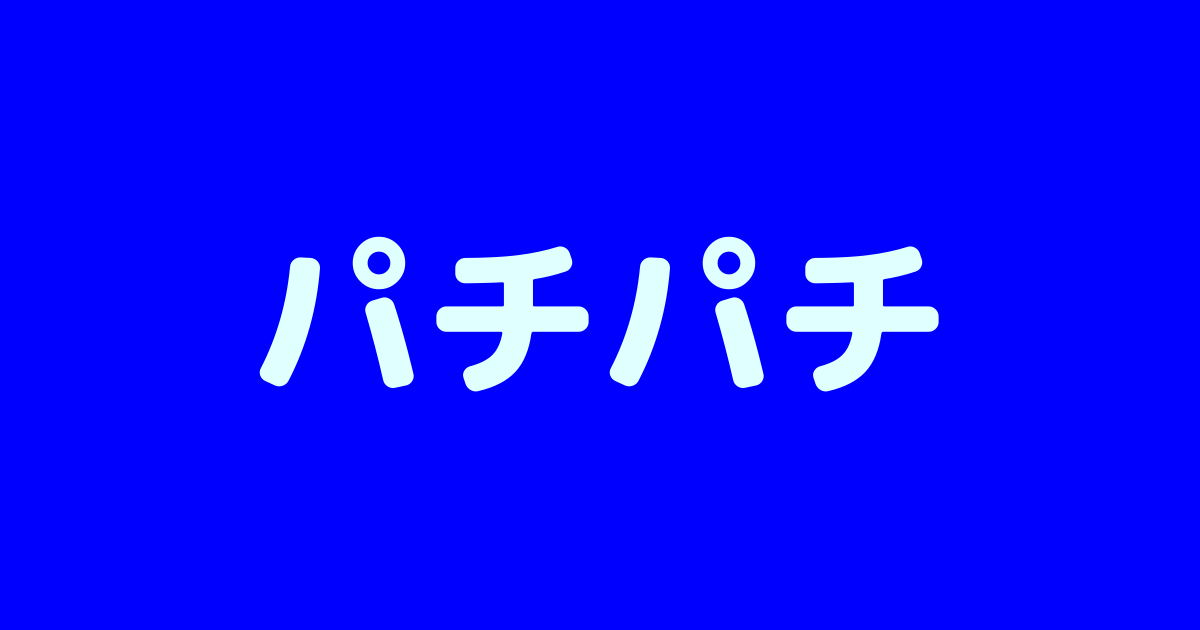
8月8日は「そろばんの日」です。
由来:そろばんを弾く音「パチパチ」という語呂合わせから。
では、そろばんを漢字では何と書くでしょうか?
「そろばん」の由来:日本に伝わったのかはっきりとしていません。が中国では算盤を「スワンパン」と読み、日本でそれを「そろばん」と読んだことが由来とされています。
また、そろばんの起源は世界中にありはっきりとはしていません。
ちなみに、そろばんで計算することを「珠算」といい
珠算では「願いましては」と読み手が数字を読み、計算をします。この「願いましては」の意味は?
「願いましては」の意味:「これから計算をお願いします」です。
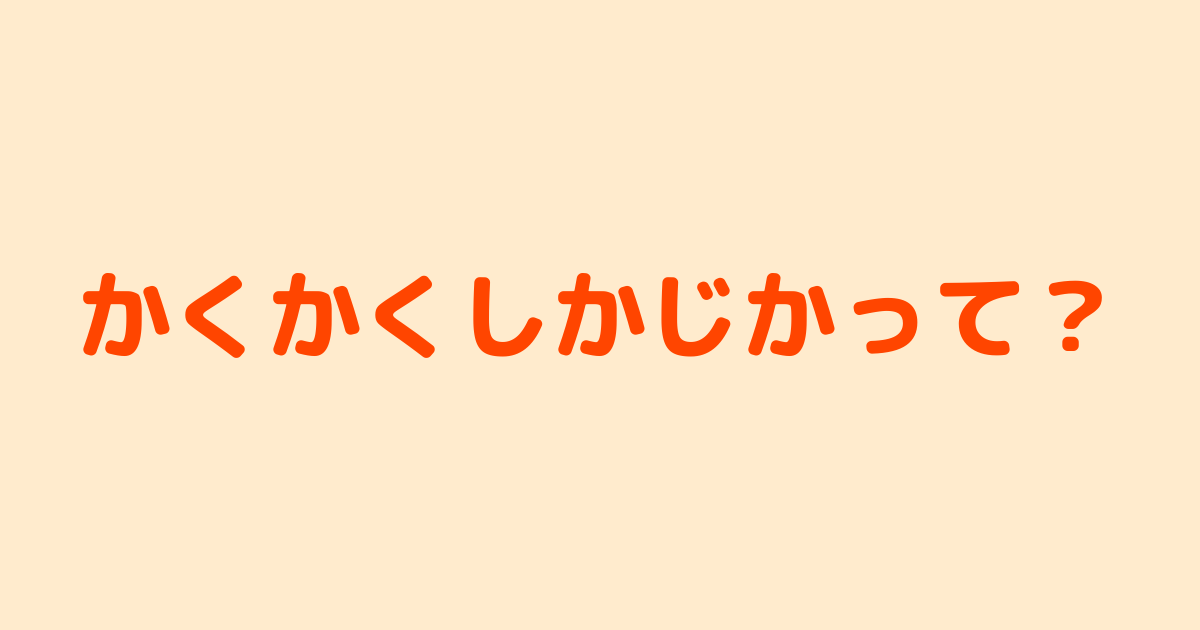
「誹謗中傷(ひぼうちゅうしょう)と一言でいいますが
この言葉は「誹謗」と「中傷」からなっています。
中傷とは?
読み方:ちゅうしょう
意味:根拠のない悪口をいいふらし、他人の名誉を傷つける
由来:「中」は食中毒などの「中」と同じ意味、なにかが中(あた)って傷つくこと
中傷の「中」は、傷の大中小など大きさのことではなく、
当たるの「中る」という意味だったのですね。
食卓用のナイフ、フォーク、スプーンはカトラリーともよばれますが、これらを漢字で表すと何なんでしょう?
ナイフ:肉刀
フォーク:肉叉(にくさ)、肉刺、肉匙、突き匙
スプーン:匙(さじ)
食卓用ではないナイフは、小刀(こがたな)があります。
匙(さじ)は日本に昔からありましたが、儀式用であったり、上流階級で使われていました。江戸時代では、医者が薬を測る道具として「お匙」と呼ばれていました。
「匙を投げる」という医者が患者を見放す比喩表現がありますが、これは医療で使われてたことが関係しているようです。
では、サボテンを漢字にすると?