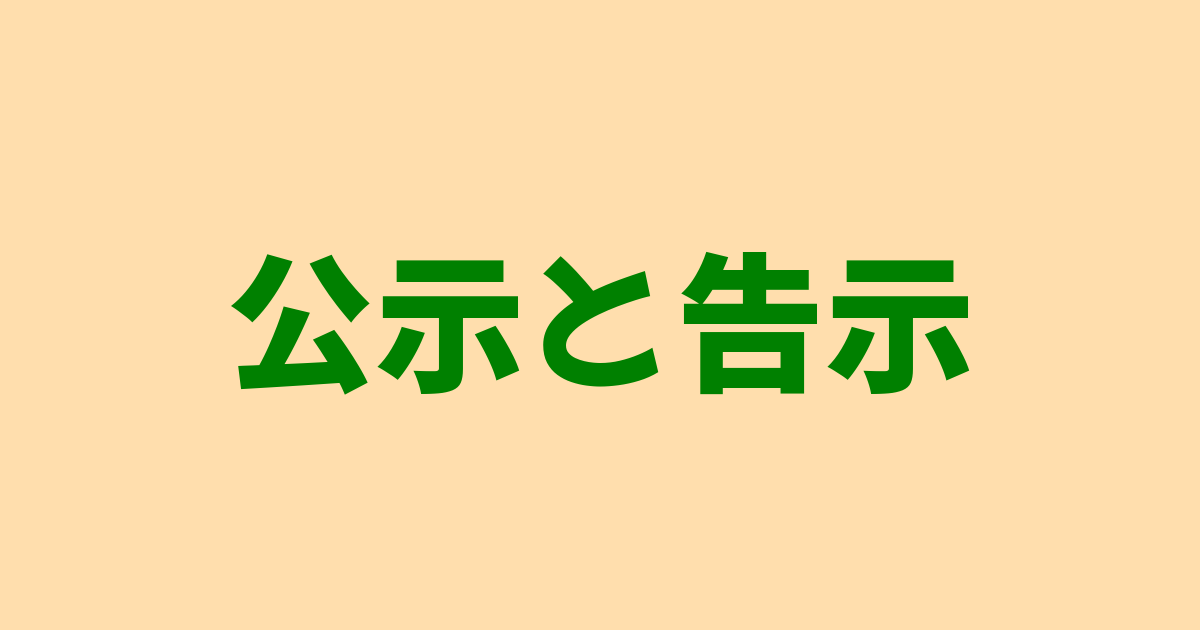今回は、改正少年法で大きく変わった点をわかりやすくご紹介します。
〇「特定少年」の位置づけ:
18歳19歳を「特定少年」とし少年法が適用され、全件家庭裁判所に送られ、家庭裁判所で処分を決定します。
ただし17歳以下と取り扱い方が一部異なります。
〇原則逆送対象事件の拡大:
殺人、傷害致死、強盗、放火、強制性交など「刑事処分を相当と認めるとき」、「16歳以上の少年が故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪の事件」など
逆送決定後、20歳以上の者と原則同様に取り扱われます。
「逆送」とは
少年審判ではなく、一般的な刑事裁判を受ける手続きのことです。
通常検察官から家庭裁判所へ送致されたものを、家庭裁判所から検察官へ再び送致すると。
〇実名報道の解禁:
起訴された段階で、実名報道が解禁されます。ただし略式請求された場合は除きます。
〇保護処分について:
特定少年の保護観察は6か月もしくは2年、少年院送致は3年の範囲内で明示されます。
改正前は、少年審判で保護処分や少年院送致となった場合、
その期間は明示されず、終期は少年の更生の実態に柔軟に運用されていました。
保護処分は要保護性から「犯情の軽重を考慮する」と明記されます。
「犯情」とは
犯罪に関わる事情全てのこと(動機、態様、計画性、被害の程度など)
〇不定期刑の適用除外:
不定期刑とは、「懲役〇年以上〇年以下」というような範囲内で刑を言い渡すことです。
長期15年、短期10年を超えないとしてました。
これを特定少年は、明確な期間「懲役〇年」(20歳以上と同様、最長30年以下)と刑を言い渡すことになります。
〇虞犯少年の適用除外:
特定少年は保護の対象から外れ少年審判に付することができなくなります。
「虞犯(ぐ犯)少年」とは
実際には罪を犯していないが、将来的に罪を犯す恐れのある少年のうち、一定の事由に当てはまる少年のこと。
では、「要請・要望・要求・依頼」の意味と違いは?