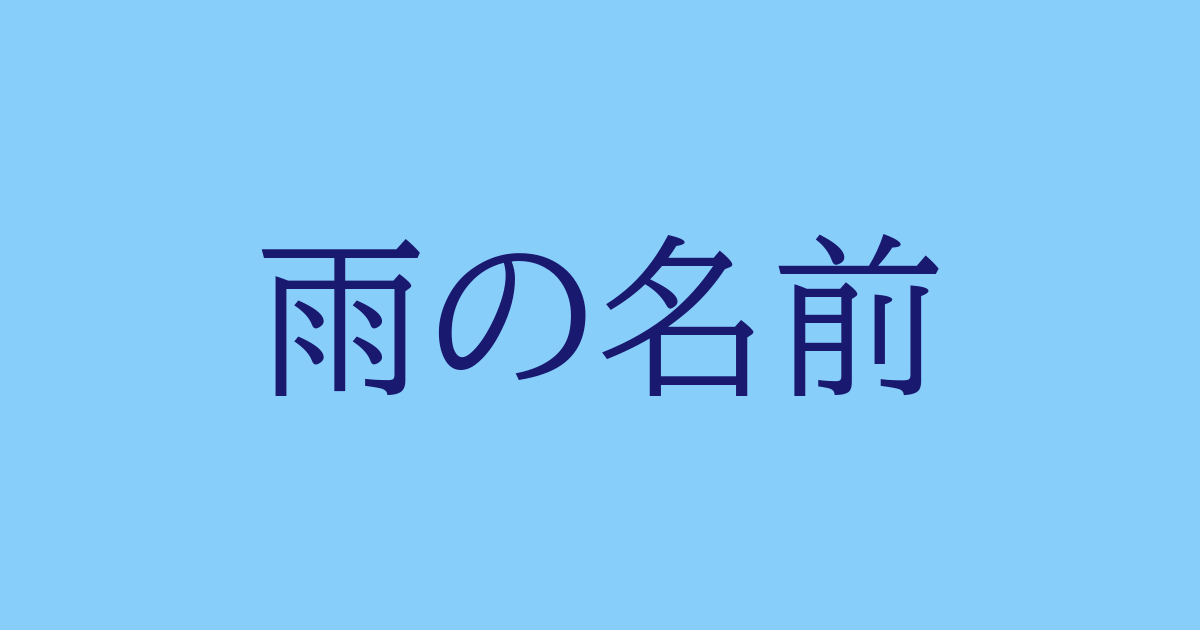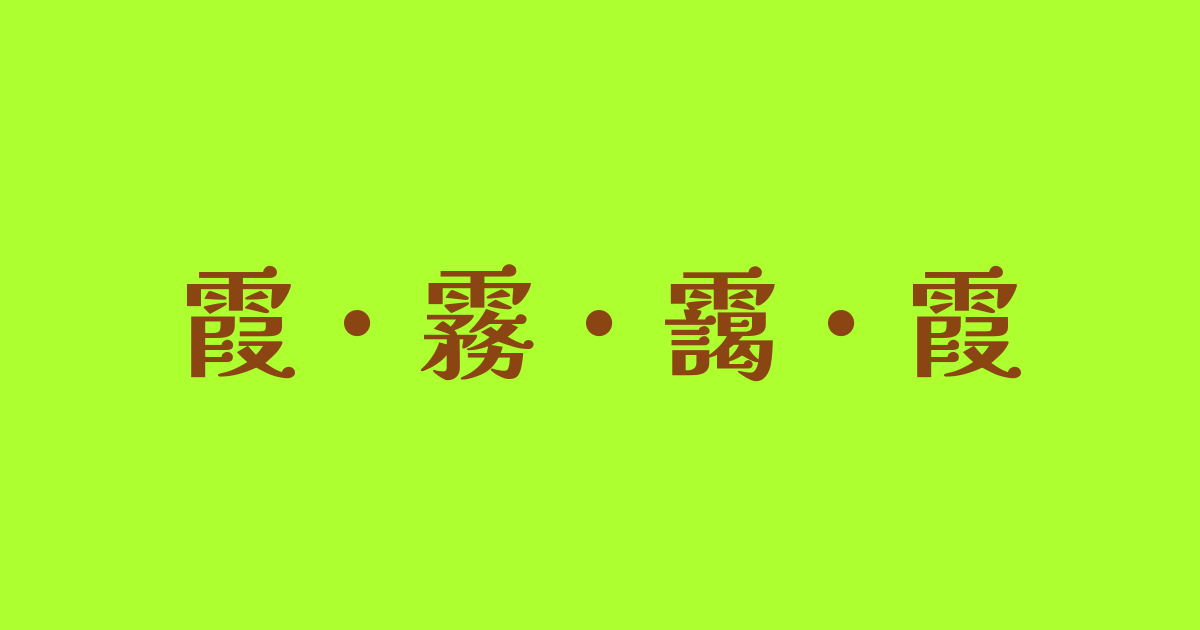老いの初め、と書いて「初老」
若々しさからは離れているイメージのですが
そもそも「初老」とは何でしょうか?
中国から由来した辻髪・志学・弱冠・而立・不惑・知命・耳順・従心などの中の「不惑」に当たるのが初老だと言われています。
「初老」とは何歳からいうのでしょうか?
孔子の論語では「四十にして惑わず」「五十にして天命を知る」とあるように、当時は40歳位から「不惑」、つまり「初老」と認識されていたようです。
「中老」とは何歳からいうのでしょうか?
40歳くらいから50歳を初老とするのに対し、中老は50歳すぎのことを言います。
但しこれは人生50年の頃の話なので、人生80年、100年と言われる現在だと、認識のずれがありそうですね。
では「大老」は?
尊敬されている老人の呼び名だそうです。
ちなみに「老老」とは、ひどく年を取ったさまのことだそうです。