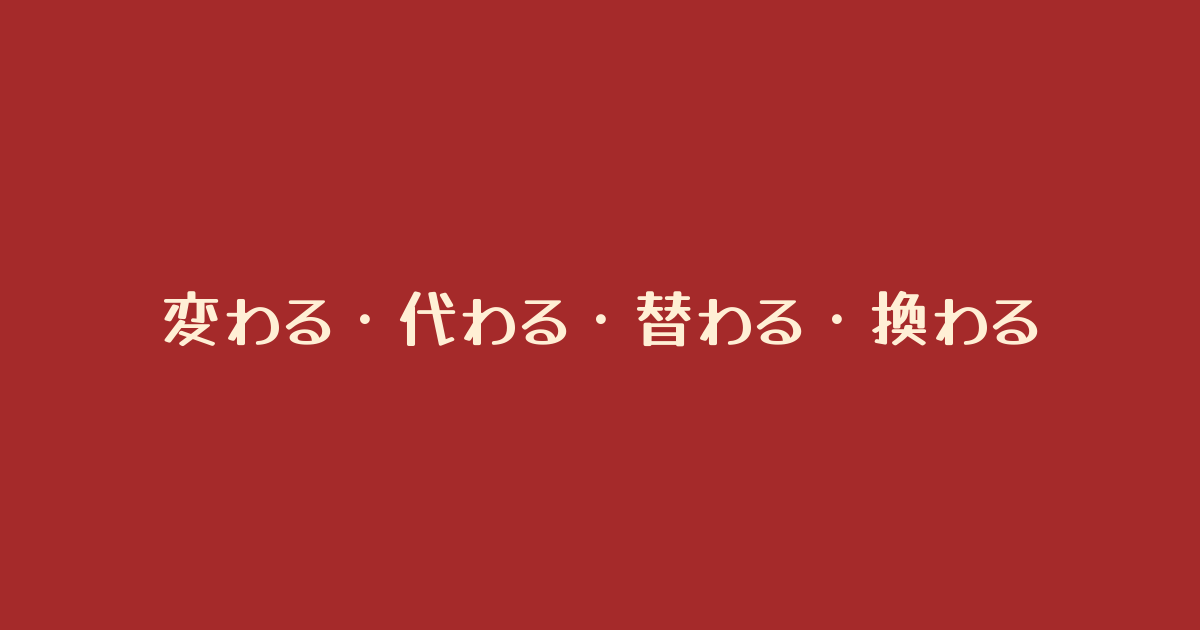「忖度(そんたく)」という言葉、2017年の流行語大賞にもなりましたが、その意味と使い方は?ときかれると、即答できないことも。今回は「忖度」の意味と使い方を、簡単に確認したいと思います。
「忖度」とは
「相手の気持ちを推し量ること」であり、相手に対する思いやりを表す言葉です。
相手の求めているものは何か、どう思っているのかを察し、予測する、日本の文化ともいえる言葉です。
しかし最近は、目上の人の気持ちを推測し、配慮するという意味で使われることが多くなり、
「言われたわけではないが、上司がきっと望んでいるであろうことをする」というイメージをもっている人も多いと思います。
「忖度」の使い方例文
本来「忖度」は文章で使われ、口頭では使うことがあまりない言葉ですが、ビジネスや日常生活の場面で使うとしたら・・・
・お客様の気持ちを忖度し、新しい提案をする。
・親の思いを忖度し、帰宅時間を早めた。
・私は和食より洋食が好みだが、友人の好みを忖度し、ランチは和食にした。
・彼の気持ちは忖度しかねる
「忖度」の類義語
少しニュアンスが変わりますが、置き換えできる語をいくつかご紹介します。
推測(すいそく):今ある情報をもとに推量すること。
憶測(おくそく):自分で勝手に推測すること。
推察(すいさつ):他人の心中を想像し理解すること。
推考(すいこう):物事の道理や事情などを推測して考えること。
斟酌(しんしゃく):相手の事情や心情をくみとること。
顧慮(こりょ):気を使いあれこれ考え心をくばること。
慮る(おもんぱかる):じっくり考え、思いめぐらすこと。
「忖度」の反対語
惻隠の情(そくいんのじょう):他人に同情する、かわいそう、不憫(ふびん)など哀れにおもう気持ちのこと。
「惻隠」とは、相手を自分の下とみて思う言葉で、
「忖度」は、相手を上にみて、推し量る言葉ということですね。
ちなみに「慮る」は、「おもんぱかる」と読みますが、「おもひ(い)はかる」が転じた言い方です。「おもんばかる」ともいいます。