「大麻」とは、
読み方:たいま、おおあさ、おおぬさ
クワ科の植物で、花冠、葉を乾燥させ、
樹脂化や液体化させたもので、規制薬物である。
神事のお祓いに大麻(おおぬさ)が用いられる。
神宮の御札(お神札)は「神宮大麻」と呼ばれ、
(読み方:じんぐうたいま、じんぐうおおぬさ)
お祓いに用いる祭具のことをいいます。
伊勢神宮が発行し、多くの神社で頒布される御札(おふだ)のこと。
「大麻(たいま)」は「大麻(たいま)」でも違いますね。

「立春大吉日 喼急如律令」とは
読み方:りっしゅんだいきちじつ きゅうきゅうにょりつりょう
「立春大吉」とは、
季節の変わり目に邪気を追い払い無病息災の意味で使われます。
「立春大吉」が左右対称の文字なので、裏から見ても同じに見えます。
そのため、節分では玄関にこれを書いたお札が貼ってあると、鬼が家に入っても、振り返った時また「立春大吉」というお札を目にし「この家にはまだ入っていない」と勘違いをして逆に出ていく。
つまり鬼が入ってこないということから、厄除けの意味として使われているのです。
「喼急如律令」とは
中国の漢時代に公文書の末尾に記される言葉で、
意味は「急いで律令のごとく行え」です。
陰陽師や祈祷師が、悪霊退散などの呪文の最後に用いました。
つまり「立春大吉日 喼急如律令」とは
「季節の変わり目、一年の始まりのめでたい日の立春、厄災は立ち去り、願いが早急にかないますように」という意味なのです。
「立春大吉」のお札は神社でいただいたり、自分で書いて貼るのも良いそうですので、是非取り入れてみるのもいいですね。では、2020年の立春はいつ?
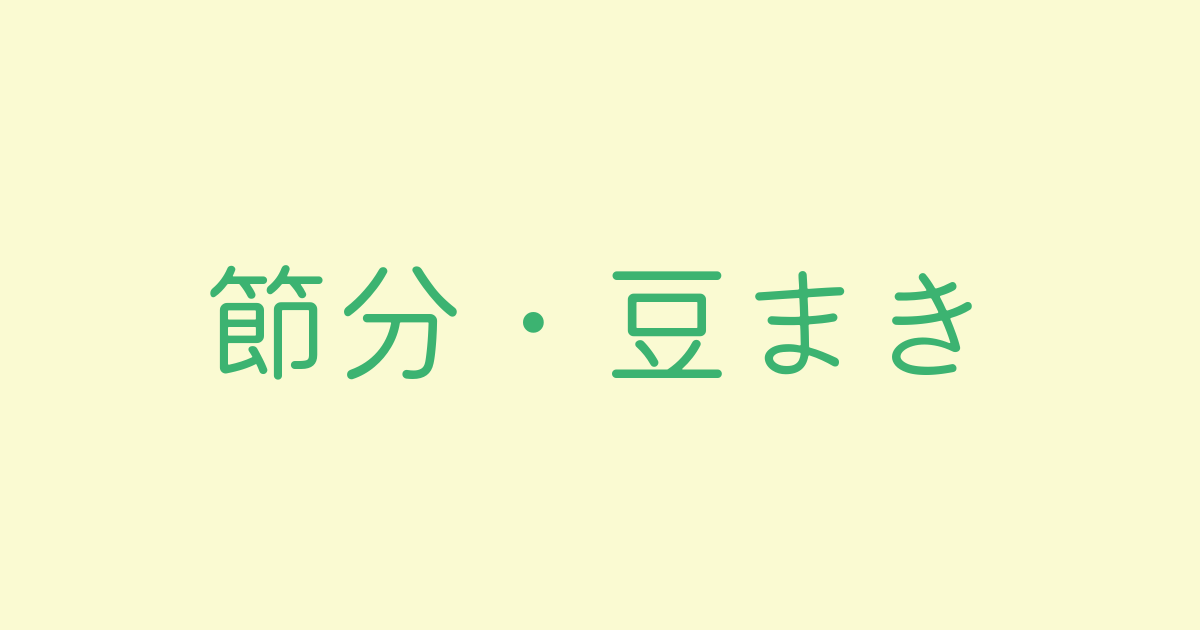
「節分」と「豆まき」の由来についてご紹介いたします。
節分は、立春の前日。
意味は「季節の分かれ目」です。
季節の分かれ目は邪気が入りやすいとされ、
その邪気を払う儀式として「豆まき」が昔から行われてきました。
ではなぜ豆をまくのか?
古来より日本では穀物には「邪気を払う力」があるとされてきました。
諸説ありますが、大豆を鬼の目に投げつけ、鬼を退治した説。
「魔目(魔の目)」に豆を投げつけ「魔滅(魔を滅する)」に通じるなど。
また、豆まきは「炒った豆」で行います。
生の豆では、芽が出て縁起が悪く、「炒る」は「射る」に通じるともいわれているためです。
地域によっては大豆ではなく、落花生をまくところもあるそうです。あなたの周りはどちらでしょうか?
旧正月・春節・立春の意味と違いについて
「旧正月」とは旧暦(太陰太陽暦)のお正月(1月1日)のことです。
日本では現在、新暦(グレゴリオ暦)が採用されていますが、明治の改暦までは旧暦が用いられていました。
太陰太陽暦とは、月の満ち欠けと太陽の動きを入れた暦です。
「春節(しゅんせつ)」とは、中国での旧正月のことで、
旧暦1月1日に始まり15日間続く祭りのこと。
ちなみに2020年は1月25日が一日目となります。
月の満ち欠けにより変わるため、毎年同じ日付ではありません。その年のカレンダーで確認しましょう。
では「立春」は?
「立春(りっしゅん)」とは
二十四節気の一つであり、旧暦ではこの日が1一年の始まりとされ、暦のうえでは春になります。
二十四節気は、太陽の動きをもとに24等分したもので、古代中国で考案されました。2020年は2月4日が立春です。
つまり月の動きを基準にした「旧正月」と「春節」は同じ意味ですが、太陽の動きをもとにした二十四節気の「立春」は別物ということです。
では「立春」以外の二十四節気の意味と由来は?
年が明けると初夢が話題にあがりまね。「初夢」はその内容で新年の運勢を占う夢占いの一種ですが、いつ見た夢のことでしょうか?
元日の夜?2日の夜?
古くは立春が一年の始まりとされていたので、節分の夜みる夢とされ、その後「事始め」が1月2日であることから2日の夜に見る夢と変わりました。
現在では「その年最初に見る夢」または
「元日の夜または1月2日の夜に見る夢」が一般的のようです。
では初夢で見ると縁起がいいといわれる
「一富士二鷹三茄子(いちふじにたかさんなすび)」その意味、由来は
一、富士…「不死、無事」の意味
二、鷹…「高、貴」に通じ、立身出世を意味
三、茄子…財を成す、事を成すの意味
そして「一富士二鷹三茄子」の続きがあります。
「四扇五煙草六座頭(しおうぎごたばころくざとう)」です。
四、扇…末広がりを意味
五、煙草…煙草の煙は上に上がることから、上に上がる縁起が良いもの
六、座頭…座頭は剃髪した盲人のことで「毛が無い」→「怪我が無い」の意味
初夢、どんな内容か楽しみですね。
2019年12月22日は冬至(とうじ)です。
冬至には、カボチャを食べて、ゆず湯に入る風習がありますが、それはなぜでしょう?
その由来をご紹介いたします。
まず、冬至とは
夏至と反対に1年でもっとも夜が長い日。
「日短きこと至る(きわまる)」という意味で、
中国では、この日から新年の始まる日とされます。
陰の気が極まり再び陽にかえる意の「一陽来復(いちようらいふく)」といい、
冬至を境に運が向いてくるとされます。
ではなぜ冬至に南瓜(かぼちゃ)を食べるのか?
冬至には「ん」のつくものを食べると「運」がつくという言い伝えから。
特に次の7種類を「ん」のつく「冬至の七種(ななくさ)」と呼びます。
南瓜(なんきん)
人参(にんじん)
蓮根(れんこん)
銀杏(ぎんなん)
金柑(きんかん)
寒天(かんてん)
うんどん(うどん)
ゆず湯に入るのはなぜ?
柚子(ゆず)は、「融通」がきく
冬至は、「湯治」のごろ合わせから。
一陽来復のために身を清めるという考えからも、
禊(みそぎ)の儀式として邪気を払うため、
香りの強い柚子湯に入ると考えられています。
二十四節気とは、
その昔、中国で季節を表す暦のようなものとして考案された手法です。
1年の長さをを12の「中気(ちゅうき)」と12の「節気(せっき)」に分け、それらに季節を表す名前がつけられたものです。
日本では江戸時代の頃から使われていたとか。
二十四節気の順番、意味、由来
1. 立春(りっしゅん)
旧暦では立春が一年の始まりとされ、暦のうえでは春になります。
2.雨水(うすい)
雪から雨に変わり、氷が溶けて水になる、という意味。
3.啓蟄(けいちつ)
啓は「ひらく」、蟄(ちつ)は「土中で冬ごもりしている虫」の意味で、
大地が暖まり冬眠していた虫が、穴から出てくる頃という7意味。
4. 春分(しゅんぶん)
太陽が真東から昇って真西に沈み、昼と夜の長さがほぼ同じになる日。
ちなみに、ヨーロッパなどでは、春分が春の始まりとされています。
5. 清明(せいめい)
万物がけがれなく生き生きとしているという「清浄明潔」という語を略したもの。
6.穀雨(こくう)
春雨が百穀を潤すことから名づけられたもの。
雨が多いというわけではなく、穀雨以降、降雨量が多くなり始めます。
7.立夏(りっか)
暦のうえでは夏になります。
8.小満(しょうまん)
陽気が良くなり、万物の成長する気が次第に長じて天地に満ち始めるという意味。
9.芒種(ぼうしゅ)
芒(のぎ)という穂先に毛のような部分あるの穀物(稲や麦など)の種をまく季節の意味。
10.夏至(げし)
太陽がもっとも高く登り、一年で、昼間が最も長く、夜が最も短い日。
11.小暑(しょうしょ)
梅雨が明けて、だんだん暑さが増していくという意味。
12.大暑(たいしょ)
夏の暑さが本格的になるという意味。
13.立秋(りっしゅう)
暦のうえでは秋になります。
14.処暑(しょしょ)
夏が過ぎ、暑さが和らぐという意味。
15.白露(はくろ)
草の葉に白い露がつき始めるという意味。
16.秋分(しゅうぶん)
春分と同じく、昼と夜の長さがほぼ同じになる日。
17.寒露(かんろ)
草木に冷たい露がつく、という意味。
18.霜降(そうこう)
朝晩の冷え込みが厳しくなり、霜が降りるという意味。
19.立冬(りっとう)
暦のうえでは冬になります。
20.小雪(しょうせつ)
多くはないが雪が降り始め、雨が雪に変わるという意味。
21.大雪(たいせつ)
本格的な冬の到来になる時期。
22.冬至(とうじ)
夏至と反対に、1年でもっとも夜が長い日。「日短きこと至る(きわまる)」という意味。
中国では、この日から新年の始まる日とされます。
23.小寒(しょうかん)
この日を「寒の入り」といい、寒さが始まるという意味。
24.大寒(だいかん)
寒さがもっとも厳しい時期。
2019年11月8日は「立冬」です。
古代中国で考案された「二十四節気(にじゅうしせっき)」の一つ「立冬(りっとう)」ですが、
立春、立夏、立秋、立冬は季節の大きな節目で、この4つを四立(しりゅう)といいます。
「立」には新しい季節になるという意味があります。
「立冬」とは、冬の始まりのことで、同様に「立春(りっしゅん)」は春の始まりとい意味です。
では、「冬はいつから?いつまで?」の答え
「立冬から立春の前日まで」が正解となります。
そして来年の立春は2020年2月4日なので、今シーズンの冬は「2019年11月8日から2020年2月3日」ということになります。
あくまで暦の上の冬ですが、、
暦の上の四立、毎年同じ日付とは限りませんので、
その年のカレンダーで確認しましょう。