ニュースで「日銀連続指し値オペ実施」や「指値オペ」という言葉を目にしました。
この「指値オペ」は何と読むのでしょうか?また「オペ」は何の意味でしょうか?
指値オペ(指し値オペ)とは
読み方:さしねおぺ
意味:指し値オペレーションの略
日本銀行(日銀)が指定する利回りで国債を買い入れる手法。
将来利回りが大きく上がることを想定とし、長期金利上昇を抑え、
低利回りで無制限に国債を買い入れることができます。

「ICT技術」の「ICT」とは何でしょうか?
英語:Information and Communication Technologyの略
日本語訳:情報通信技術
意味:情報技術の(IT)を活用したコミュニケーションの総称
例えば、学校教育現場で使われるPCやタブレット教材
高齢者のみまもりシステム、テレワーク、自動走行車など
ODRとは何のことでしょうか?簡単にご紹介します。
ODRとは
英語:Online Dispute Resolutionの略
日本語訳:オンライン紛争解決
意味:裁判によらないICT技術での紛争解決手段
インターネット上で紛争の予防、管理、解決まで全てを行うことです。
このサービスによるメリットは、
時間や場所、障害のあるなし、言語の違いに左右されないこと。
移動など費用の面も少なくなります。
非接触、実際には対面しないので、感染症対策にも活用可能です。
ちなみに、オンライン紛争解決の「紛争」とは
もめ事の意味。
国家間の戦争や、企業と消費者間、家庭内など個人間の揉め事のことをいいます。
「EU、即応部隊の創設」などニュースや新聞で目にしました。「即応」とは、状況、情勢に素早く対応、行動するという意味ですが、即応部隊とは何でしょうか?
即応部隊とは
英語では「rapid reaction force」
主に危機時の人命救助、市民の退避を担ったり平和維持活動などが目的とされます。
世界にある即応部隊の例として
欧州即応部隊
英語:European Operational Rapid Force(略称:Eurofor)
目的:人道支援、平和維持活動など
構成:フランス、イタリア、ポルトガル、スペインからなる多国籍軍
NATO即応部隊(北大西洋条約機構即応部隊)
英語:NATO Response Force(略称:NRF)
目的:集団的自衛権、危機管理など
構成:NATO加盟国の陸海空部隊からの連合軍
では、将官と将校の違いは?
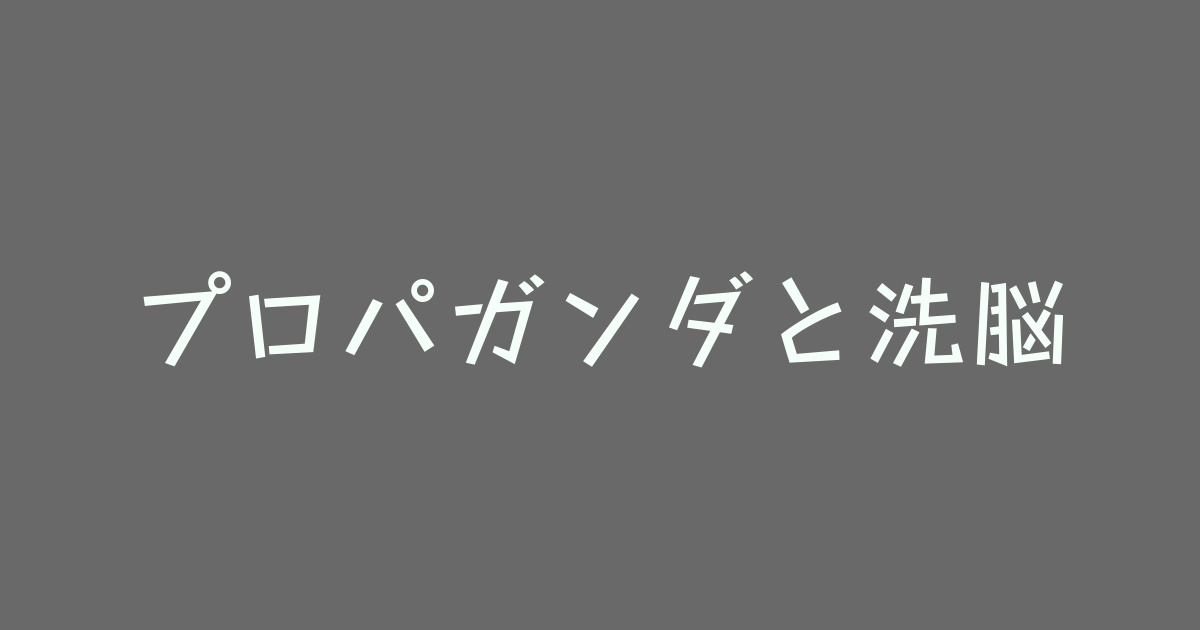
「プロパガンダ」と「洗脳」はどう違うのでしょうか?
「プロパガンダ」とは
英語:propaganda
意味:意図した方向へ仕向けようとする行動
宣伝、特に政治的な宣伝行為を指します。
政治的なプロパガンダの例:
戦争を起こそうと政府が国民に対して危機感を煽るための情報操作
語源:ラテン語の「種をまく:propagare」という言葉から
「洗脳」とは
意味:思想改造のこと
個人の思想、価値観を、特異な環境下で根本的に改めさせ、強制的に植え付けること。
第二次世界大戦後、中国で反革命分子とされる人(知識人など)に行われた自己改革や自己改造を指した言葉
英語では「brainwashing」
「特定少年」とは何でしょうか?その意味と、改正少年法がいつから始まるのかをご紹介します。
成人が20歳から18歳へ引き下げられ、少年法も改正されました。その施行は2022年(令和4年)4月1日です。
まず、少年法とは
適用対象:20歳に満たない者
目的は「少年の健全な育成」であり、少年は成人と異なり実名報道原則禁止など保護されます。
全件家庭裁判所に送られ、家庭裁判所で処分を決定します。
では、改正少年法とは
適用対象:20歳未満(改正前と同じ)
ただし18歳19歳は「特定少年」とし17歳以下と区別されます。
18歳19歳は、少年法は適用されますが、17歳以下と取り扱い方が一部異なります。
「特定少年」の位置づけのほか、逆送致対象事件の拡大、実名報道の解禁などが特に大きく変わりました。
今回は、改正少年法で大きく変わった点をわかりやすくご紹介します。
〇「特定少年」の位置づけ:
18歳19歳を「特定少年」とし少年法が適用され、全件家庭裁判所に送られ、家庭裁判所で処分を決定します。
ただし17歳以下と取り扱い方が一部異なります。
〇原則逆送対象事件の拡大:
殺人、傷害致死、強盗、放火、強制性交など「刑事処分を相当と認めるとき」、「16歳以上の少年が故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪の事件」など
逆送決定後、20歳以上の者と原則同様に取り扱われます。
「逆送」とは
少年審判ではなく、一般的な刑事裁判を受ける手続きのことです。
通常検察官から家庭裁判所へ送致されたものを、家庭裁判所から検察官へ再び送致すると。
〇実名報道の解禁:
起訴された段階で、実名報道が解禁されます。ただし略式請求された場合は除きます。
〇保護処分について:
特定少年の保護観察は6か月もしくは2年、少年院送致は3年の範囲内で明示されます。
改正前は、少年審判で保護処分や少年院送致となった場合、
その期間は明示されず、終期は少年の更生の実態に柔軟に運用されていました。
保護処分は要保護性から「犯情の軽重を考慮する」と明記されます。
「犯情」とは
犯罪に関わる事情全てのこと(動機、態様、計画性、被害の程度など)
〇不定期刑の適用除外:
不定期刑とは、「懲役〇年以上〇年以下」というような範囲内で刑を言い渡すことです。
長期15年、短期10年を超えないとしてました。
これを特定少年は、明確な期間「懲役〇年」(20歳以上と同様、最長30年以下)と刑を言い渡すことになります。
〇虞犯少年の適用除外:
特定少年は保護の対象から外れ少年審判に付することができなくなります。
「虞犯(ぐ犯)少年」とは
実際には罪を犯していないが、将来的に罪を犯す恐れのある少年のうち、一定の事由に当てはまる少年のこと。