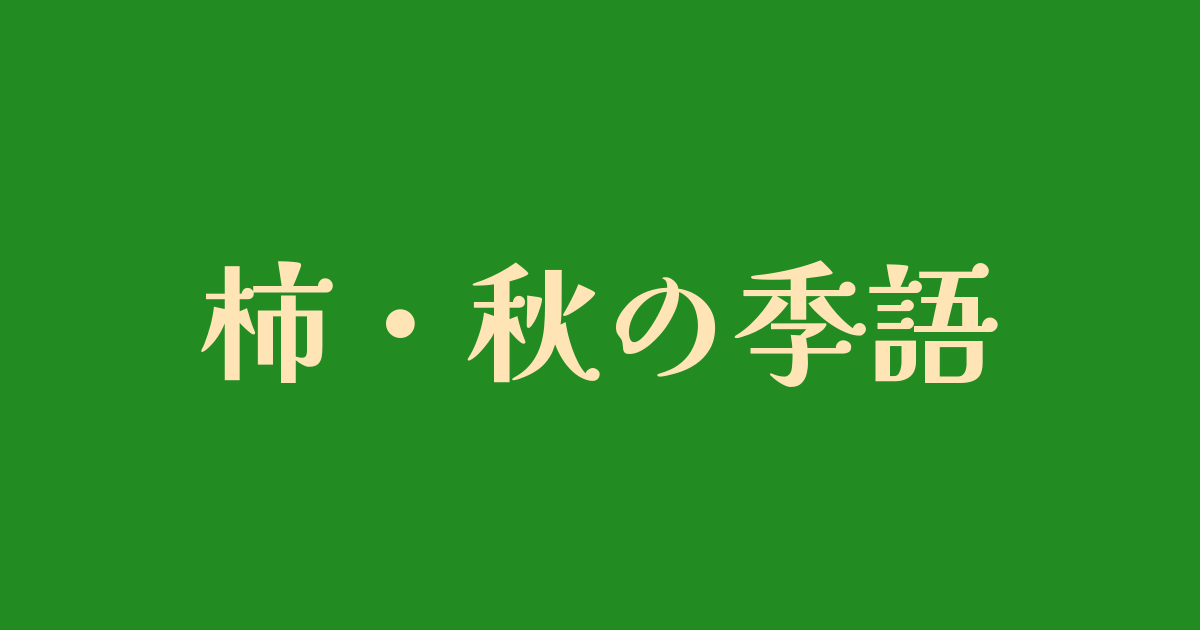秋といえば収穫の季節。色とりどりの果物が店先に並び、その美しい姿から実りの秋を感じさせてくれます。
今回は、秋の代表する果物「柿、熟柿、信濃柿」についてご紹介します。

柿は甘さと独特の食感が特徴で、日本の秋を象徴する果物です。「柿」「熟柿」「信濃柿」は、秋を感じさせる季語としても古来より用いられ「柿の秋」という言葉も生まれました。
「柿」は深い赤色が秋の風情を感じさせ、その木の姿は農村の原風景となっています。また、かつて柿はすべて渋柿であり、肉厚の渋味を抜いて食用に使われてきました。
「樽柿」「吊し柿」「干柿」など、渋味を抜く工程を表現した言葉は季語として多くの俳句に詠まれています。また、甘柿が現れたのは鎌倉時代のことです。
「熟柿」は、完熟した柿のことを指し、皮が滑らかに剥け、中身はやわらかくとろっとして甘みが強くなっています。
「信濃柿」は、小さな果実の柿で、一般的に1~2cm程度で連なるように実ります。この柿は古くから栽培され、特に信濃地方に多いことからその名がつきました。
未熟の果実から柿渋を取るために栽培され、また材木としても利用されています。晩秋に霜が当たり黒っぽく熟したものは、甘くて食用になります。

「柿」に関係する秋の季語・意味一覧
渋柿(しぶがき)、渋みの抜けない柿
樽柿(たるがき)、渋柿を空いた酒樽にい入れ酒気で渋みをぬくこと
干柿(ほしがき)、渋柿の皮をむいて干したもの
串柿(くしがき)、渋柿の皮をむき串にさして干したもの
転柿(ころがき)、皮をむき天日干しした柿のこと
吊るし柿(つるしがき)、渋柿の皮をむき縄などに吊るして干した
甘干(あまぼし)、渋柿の皮をむいて少し乾かしたもの
柿干す(かきほす)、渋柿の皮をむき干したもの
柿吊す(かきつるす)、渋柿の皮をむき縄などで吊るしたもの
甘柿(あまがき)、渋みのない柿
きざわし、きざらし、木醂柿(きざがき)、甘柿の別称
木練柿(こねりがき)、木になったまま熟す柿のこと
熟柿(じゅくし)、熟した柿

会津身知らず柿(あいずみしらずかき)、福島県の会津地方で栽培されている柿
赤柿(あかがき)、「富有柿」と「次郎柿」を掛け合わせた「陽豊柿」の別名でとても紅く甘い
富有柿(ふゆうがき)、岐阜県原産の甘柿
御所柿(ごしょがき)、奈良県御所市で栽培されている柿
似柿(にたりがき)、御所柿に似ている柿
次郎柿(じろうがき)、静岡県原産で栽培されている柿
伽羅柿(きゃらがき)、佐賀県原産で栽培されている柿
西条柿(さいじょうがき)、広島県で栽培されている柿
柿羊羹(かきようかん)、柿を主原料とした和菓子
山柿(やまがき)、柿の変種
柿膾(かきなます)、大根と人参のなますに干し柿を加えたもの
柿店(かきみせ)、柿が並んだ店
柿の蔕落ち(かきのほぞおち)、良く熟した柿がヘタから落ちること

ちなみに、柿の木には「木守柿」という習慣があります。熟した柿を全部収穫せずに1個か2個枝に残しておき、来年の豊作を祈る習わしです。柿の木は霊木としても考えられ、あの世とこの世を結ぶと信じられ、日本の生活に深く根付いています。
柿は美味しいだけでなく、見た目の美しさからも秋の風情を感じさせてくれます。柿の季節は、木守柿を探しながら楽しむのもいいですね。