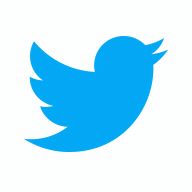「鬼灯」「鬼燈」「酸漿」は同じ読み方をします。さて何と読むでしょうか?
答え・・・
「ほおずき」です。
「鬼灯、鬼燈、酸漿」は日本ではお盆の頃に飾られ、
袋状の赤いガクに包まれた実をつけるナス科植物です。
ほおずきの由来・語源:
赤い袋状の実を頬に例えた説。
実を口に含み鳴らす遊びをする子供が頬を突き合わせる様子の「頬突き」説。
お盆に飾る小さな文月提灯に似ていることから「文月」が転じたという説。
ホホというカメムシの仲間がよく付くためなど多々あります。
「鬼灯」の由来:祖先がお盆に帰ってくるときの目印、提灯の代わりに飾られたことから。
「酸漿」の由来:根は「酸漿根(さんしょうこん)」という生薬になり、その名前から。
ホオズキの別名:「輝血」、「赤輝血」、「赤加賀智」、「酸漿(ぬかずき)」
英語では「Chinese lantern plant」です。
英語と日本語の「鬼灯」「鬼燈」は似た表現ですね。