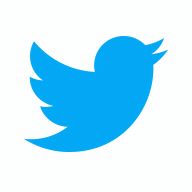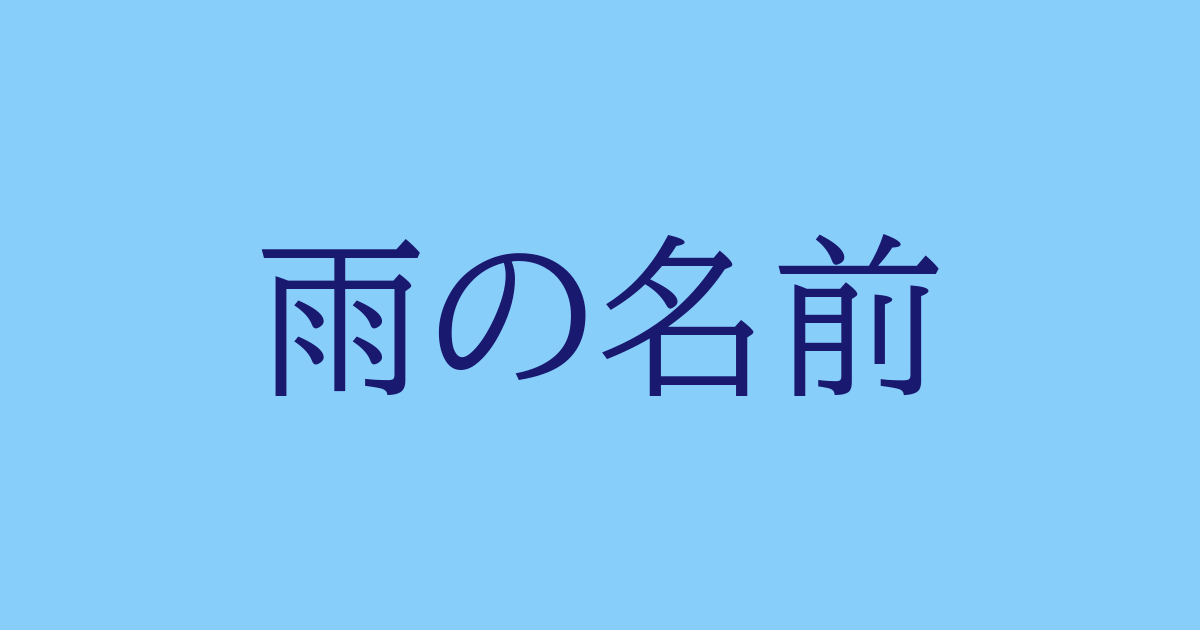雨の種類はどれくらいあるのでしょうか?
気象予報で使われる用語では、
霧雨、雷雨、長雨、風雨、夕立などですが、
それ以外に、日本には四百以上の呼び名があるとか。
季節ごとの呼び名も様々あり、
例えば、秋の雨の場合
冷雨(れいう、ひさめ)、しとしと降る冷たい雨
白驟雨(はくしゅうう)、断続的に激しく降る雨
秋微雨(あきついり)、秋入梅とも書き、梅雨の様な長雨
秋湿り(あきしめり)、秋の長雨
秋霖(しゅうりん)、すすき梅雨ともいい、梅雨の様な長雨
伊勢清めの雨(いせきよめのあめ)、
宮中行事の「神嘗祭(かんなめさい)」(陰暦9月17日)の翌日に降る雨
秋でも、梅雨の様な長雨の表現が多数ありますが、
実は一年のうち4回、雨の降りやすい時期があるそうです。
冬から春は、「菜種梅雨」
春から夏は、梅の実が熟す季節の「梅雨」
秋、ススキの季節の「秋霖」
冬、さざんかの咲く季節の「山茶花梅雨」または「山茶花時雨」
雨と一言で言っても、その表現はとても豊かですね。