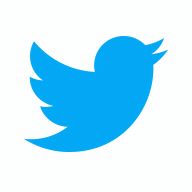「発足」の読み方は「はっそく」「ほっそく」どちらでしょうか?
答え「はっそく」と「ほっそく」
どちらも正しい読みです。
しかし、現在は「ほっそく」の読み方が一般的とされています。
「発足」の意味
組織や団体などが活動を始めること。
出発すること。
「発」を「はつ」と読むのは漢音、
「ほつ」と読むのは呉音とされています。
呉音は仏教の言葉や漢音が伝わる前に定着していた日本語によく使われています。
室町時代の書物『日葡辞書』(にっぽじしょ。)には
「発足」を「はっそく」「ほっそく」の両方の読みが記載されており、その頃はどちらも一般的に使われていたと考えられます。